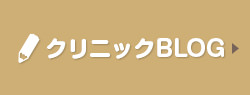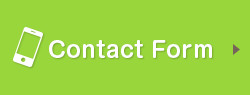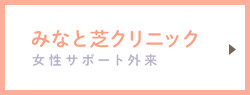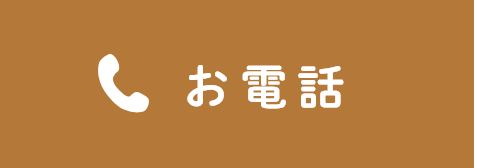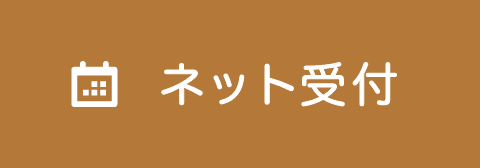2025.10.16更新
「腸乾燥」は、漢方医学で用いられる用語で、体内の水分不足や血(けつ)の不足により腸が乾燥し、便が硬くなって排便が困難になる状態を指します。便秘解消のためには、潤いを与える食材(ナッツ類、あんず、松の実など)の摂取や水分補給、規則正しい生活習慣、そして「潤腸湯」や「麻子仁丸」といった漢方薬が用いられることがあります。
「腸乾燥」を放置しておくとどうなる?
腸内環境の悪化と便の滞留
水分が不足して便が乾燥すると、腸のぜん動運動が鈍り、便が腸内に停滞しやすくなります。硬くなった便が腸壁を傷つけ、さらに便秘を悪化させる可能性があります。
全身への悪影響
滞留した便から発生した毒素が血流に乗って全身を巡り、免疫力の低下、肥満、肌のトラブル(乾燥、ニキビ、くすみ)などを引き起こします。
消化吸収への影響
栄養吸収に時間がかかり、余分な栄養が吸収されて肥満につながることもあります。
便秘の慢性化と腸機能の低下
特に子供の場合、便秘を放置すると正しい排便機能が備わらず、大人になっても便秘に悩まされることがあります。シニア世代では、腸の感受性が低下し、便意を感じにくくなることも便秘悪化の一因です。
精神的な影響
便秘による不快感から、イライラしたり、食欲不振に陥ったりすることもあります。
重篤な疾患のリスク
長期間放置すると、大腸がんや、糖尿病などの代謝系疾患、うつなど神経・脳関連のトラブルにつながる可能性も指摘されています。
*:過敏性腸症候群(IBS)の可能性
腸の異常がないのに、コロコロした硬い便が出たり、下痢と便秘を繰り返したりする病気です。 適切な治療を行えば、改善します。
「腸の乾燥」を防ぐ食材1~5位とその理由
山芋
ペクチン、ガラクタン(多糖類)、マンナン(糖タンパク)、レジスタントスターチ(難消化性デンプン)という水溶性食物繊維と似たような働きがあり、善玉菌のエサとなる。
キウイ
ペクチンという水溶性食物繊維がフルーツの中で一番豊富(水溶性0.6g。不溶性2.0g)、マグネシウム、カリウムも豊富で、便の水分が増し、ぜん動運動が亢進する。
きくらげ
不溶性、水溶性食物繊維の割合が11:1と不溶性食物繊維が豊富なため、便の量が増え腸を刺激してぜん動運動が亢進する。ビタミンDが多く、腸内環境が良くなる効果がある。
アーモンド
マグネシウムを多く含む。酸化マグネシウムには水分を吸収する働きがあり、浸透圧の働きによって腸内の水分量が増えると、その水分を酸化マグネシウムが吸収して腸内の水分量が増加します。こうして便が柔らかく膨張するため腸内の動きが活性化される。
杏仁
漢方薬の潤腸湯や麻子仁丸の成分。麻子仁(マシニン)と杏仁(キョウニン)の働き:麻子仁と杏仁に含まれる油分が腸管のクロライドチャネル(CFTR)やカリウムチャネル(BK)を活性化させ、腸上皮細胞から腸管内へカリウムイオンとクロライドイオンを同時流出させます。その際、水分が電解質とともに移動します。
「腸の乾燥 」を防ぐ習慣1~5位とその理由
- 夜遅い食事は避ける(朝ごはんまで8時間以上空けると、食事をした時に大ぜん動が生じ、強い腸の収縮により排便が一気に促される)。
- 食事以外の水分を1日2L飲む
- 水分が不足すると便が硬くなるため、起床後やこまめな水分摂取をする。成人女性でも最低1日1.5リットル程度の水分摂取が推奨される(男性は2リットル)。
食物繊維の摂取
水溶性食物繊維(海藻、きのこ、果物など)と不溶性食物繊維(野菜、芋類、豆類など)をバランス良く摂り、便の材料を増やし、腸の動きを活発にする。
善玉菌を増やす
乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルト、発酵食品(味噌、キムチなど)を摂取し、腸内環境を整える。
オリゴ糖を意識して摂る:善玉菌のエサとなるオリゴ糖を含む食品(バナナ、はちみつなど)も積極的に摂り入れる。
体を温める食材
しょうが、シナモン、ゴマハチミツなど、お腹を温める食材も腸の乾燥改善に役立つ。
生活習慣の改善策
規則正しい食生活:食事を抜かず、3食バランス良く摂ることが大切。
適度な運動
軽い運動で腸のぜん動運動を促し、便通を改善する。
ストレスの軽減
ストレスは腸の動きを妨げるので、アロマバスを利用したり、リラックスできる香りの野菜(セロリ、シソなど)を取り入れたりして、ストレスを溜めないようにする。
生活リズムを整える
十分な睡眠をとり、不規則な生活習慣を改善することで、腸の働きを整える。
その他の方法
お腹のマッサージ
おへその周りを時計回りに、気持ち良いと感じる強さでゆっくりと押すと、腸の動きが刺激されます。
執筆者紹介
みなと芝クリニック 名誉院長 川本 徹
| 1987年 | 筑波大学医学専門学群卒業 |
|---|---|
| 1993年 | 筑波大学大学院医学研究科修了 博士(医学) |
| 1996年 | 筑波大学臨床医学系外科(消化器)講師 |
| 2003年 | 米国テキサス大学MDアンダーソン癌センター客員講師 |
| 2008年 | 東京女子医科大学消化器病センター外科非常勤講師 |
| 2010年5月より、 | みなと芝クリニック 院長 |
| 2013年 | 東邦大学医学部医学科 客員講師 |
| 2022年10月 | みなと芝クリニック名誉院長 |
| 2022年11月 | 犀星の杜クリニック六本木院長 |
| 専門分野 | 内科、整形外科、皮膚科 |
|---|---|
| 認定医・専門医 | 日本外科学会 認定医 日本消化器外科学会 認定医 日本消化器病学会認定消化器病専門医 日本抗加齢学会会員 |
| その他の所属学会 | 米国臨床腫瘍学会 正会員 米国癌学会 正会員 |